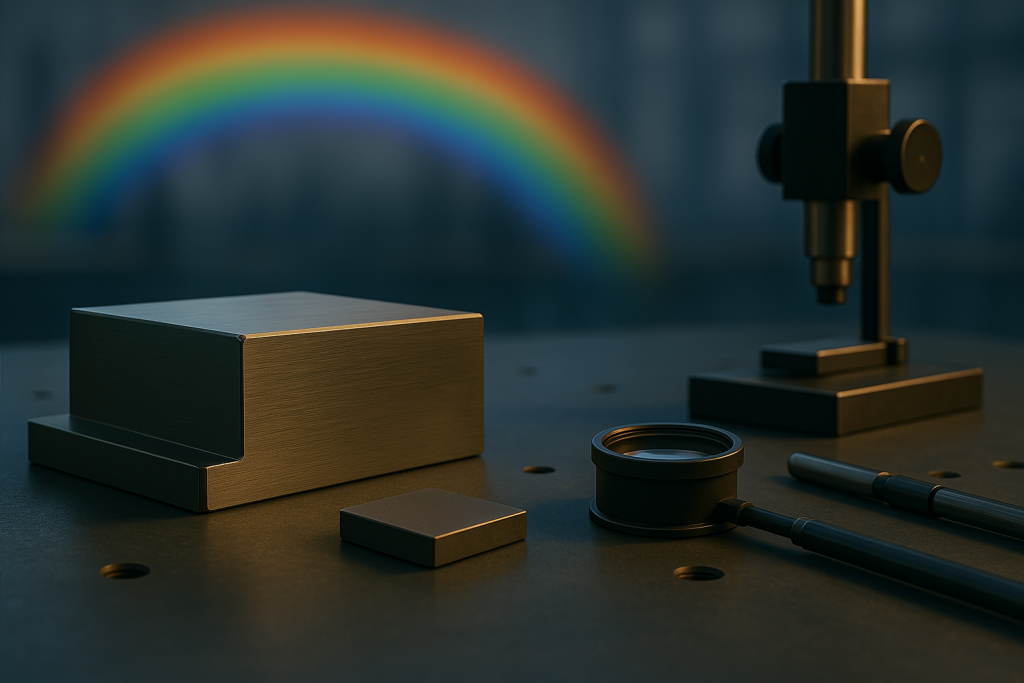
研究開発部の新井です。
今回はバリの存在について、少し哲学的なアプローチで考えてみます。
日常で何気なく使っている「バリ」という言葉ですが、よくよくその本質を見つめ直すと、意外なほどあいまいで主観的な面があることがわかります。
この記事では「虹の色の数」に関する話題を例に、バリという存在を哲学的に見つめ直し、そのあいまいさと対処法について考えてみましょう。
先日、初めて富士山を登った際、幸運にもブロッケン現象と呼ばれる珍しい虹の輪を見ることができました。
太陽と霧の位置関係が整わないと見られない、なかなか貴重な現象です。

このとき、「虹の色の数は国によって違う」という事実を思い出しました。
一般的に日本では「虹=7色」と言われますが、アメリカでは6色、ドイツでは5色、台湾のブヌン族では3色とも言われています。
出典:【虹蔵不見】何色に見えるか捉え方次第!?国で異なる虹の色 – ウェザーニュース
https://weathernews.jp/s/topics/201710/310135/
そもそも虹は、太陽光が水滴で屈折・反射して発生する光学現象です。
ところが人間は、連続的なスペクトルをそのまま認識しているのではなく、脳が光を複数の色として処理しているため、国や文化によって虹の色の数が異なるのです。
つまり虹の色は、物理的なスペクトルそのものではなく、脳が作り出す知覚です。
実はこの現象、バリの有無にも通じるのではないかと考えています。
まず、バリの定義を振り返ってみましょう。
JISによると、バリは以下のように定義されています。
「かどのエッジにおける、幾何学的な形状の外側の残留物で、機械加工又は成形工程における部品上の残留物」
(引用:JIS B 0051)
一見、客観的に見える定義ですが、実はかなりあいまいです。具体的に言えば、
・「かどのエッジ」: 角度や形状が具体的に定義されていない(鋭角なのか鈍角なのか、曲率はどうか、など)。
・「残留物」: 材質や形状、大きさなどの制限が明確ではないため、どの程度のものが「残留物」=バリとして認識されるのかが曖昧。
このように、バリは物理的に厳密に定義されるというより、人の主観によって決まる要素が強いといえます。
実際に加工現場で「バリがあるかどうか」は、どのように見つけられているのでしょうか?
当社が「バリ無きことの基準」の調査を行ったところ、以下の結果が得られました。
• 目視で確認:16%
• 触覚で確認:61%
• 測定:16%
• その他:7%
出典:「バリなきこと」が達成できる値を調査してみた | 株式会社ジーベックテクノロジー
https://www.xebec-tech.com/blog/no-3/
つまり、バリの有無はほとんどが「目視や触覚」に依存しているのです。
言い換えれば、見なければ存在しない、触らなければ存在しない、と言えるほど主観的な確認方法が中心になっています。
さらに、同じワークの同じエッジを見ても、「裸眼では見えない→バリが無い」「顕微鏡なら見える→バリがある」というように、人や道具によってバリの存在が左右されるのです。
「切削加工後にフライス盤の中でバリができているに違いない」と考えている人も多いかもしれません。
しかし、実際にマシニングセンタ稼働中のワークを直接見ることはほぼ不可能であり、「確信を持てる」ほどの客観的事実は得られません。そこには経験則(主観)が入り込むからです。
極端な話、「バリ」という概念を知らない人には、バリが認知できない=存在しない、と捉えられてしまいます。
ここまで考えると、バリとは非常に観念論的な存在と言えます。
観念論とは、「物質や自然よりも、精神や意識を根源的な原理とみなす立場」です。
出典:観念論(カンネンロン)とは? 意味や使い方 – コトバンク
https://kotobank.jp/word/%E8%A6%B3%E5%BF%B5%E8%AB%96-49438
代表的な観念論の哲学者ジョージ・バークリーの言葉に、「存在するとは知覚されることである」というものがあります。
通常、机やPC、人、山、太陽などの「物」は、見たり触ったりしていなくても存在していると考えるのが当たり前です。
けれども観念論の立場では、そうした「物」は、知覚する限りにおいてのみ存在すると捉えます。
先ほどの虹の例と同じで、日本人には藍色が見えていてもアメリカ人には藍色がない、といった違いは「知覚の有無」によるものです。
バリについても、「そこにバリがある」と知覚しなければ、そもそもバリは存在しないとも言えるわけです。
とはいえ、多くの方は「バリは確かにそこにあって、バリ取りしないといけない」という実務的な現実に直面していると思います。
観念論的に「バリがない」と言い切るわけにもいきません。ではどうすればいいのでしょうか。
設計者、検査員、バリ取り作業者、納品先、ツール販売店、バリ取りツールメーカーなど、すべての関係者が「バリという概念には幅がある」ことを共通認識として持つことが重要です。これは虹の色が国や文化で異なるのと同じです。
あいまいな存在であるバリを、なるべく共通認識化するために、定量的な指標を導入するのが理想です。
たとえば、マイクロメータやダイヤルゲージなどの接触式測定、デジタルマイクロスコープや精密測定顕微鏡などの非接触式測定を活用すると良いでしょう。
「『バリなきこと』としか指示がなく、どこまでバリを取ればいいかわからない!」
このような場合は、バリの高さ0.03mm以下をひとつの目安にすることをおすすめします。
これは当社の調査で判明した「バリの取り直しが起こりにくい高さ」の基準です。
これらを実践することで、バリの取り直しや過度な仕上げを予防し、バリ取りの効率化やコスト削減、最終的には生産性向上につなげることが可能になります。
つまり、バリが観念論的存在であると認めながらも、実務上の問題を最小化することができるのです。
今回の記事で、バリがいかにあいまいで主観的な存在であるのか、また、そのあいまいさに対処するための考え方をご紹介しました。
バリは製造現場のどこにでも発生する可能性がある一方、その基準は人によって大きく異なります。
そこで、ぜひインターモールドのジーベックテクノロジーブースにて、皆さんの「バリのあいまいさにまつわる困りごと」「独自の対処法」などをお聞かせください。
研究開発部の私(新井)が、ブース内の“手作業ツール体験コーナー”にてお待ちしております。
あいまいな存在であるバリに、我々はこれからも立ち向かっていきます。
今後の弊社の取り組みに、ぜひご期待ください!