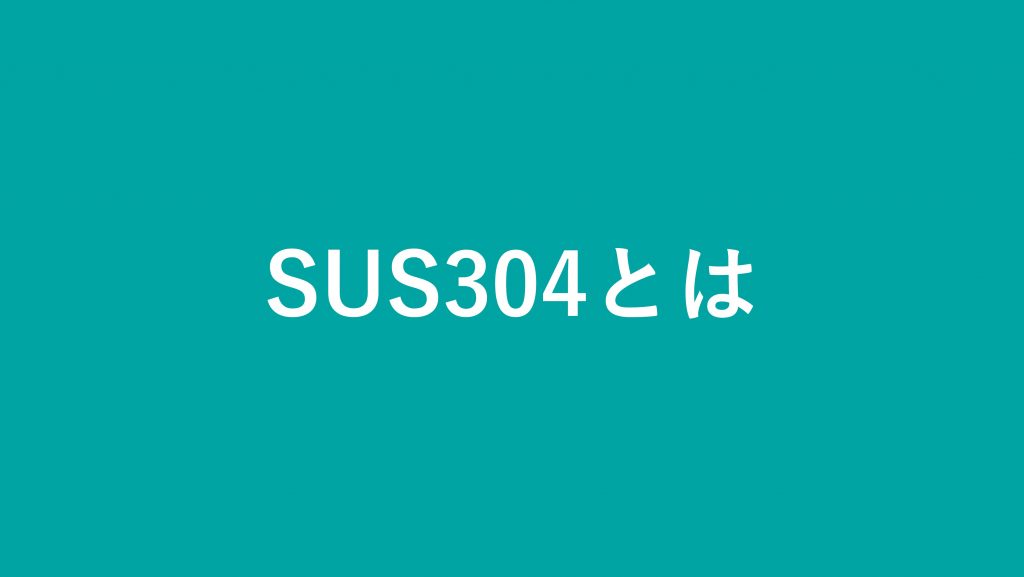
SUS304は、ステンレス鋼の中でも最も広く使われている素材です。
金属加工や製品設計に携わるのであれば、SUS304に関する知識は欠かせません。
今回はコラム記事として、SUS304について広くまとめていきます。
目次
・1.SUS304はステンレス鋼の一種
・2.SUS304の特徴
・3.SUS304の用途
・4.SUS304を構成する成分
・5.SUS304に行える表面処理
・6.SUS304の価格動向
・7.SUS304以外のステンレス
・8.SUS304のデメリットとその対策
・9.ステンレス鋼の将来展望
・10.まとめ
SUS304はステンレス鋼の一種です。
鉄をベースにクロムとニッケルを含有した「オーステナイト系ステンレス」に分類されます。
呼び方は「サスさんまるよん」です。
SUS304は加工のしやすい素材であることから、ステンレス鋼の中でも最も広く使われています。
加えてサビや腐食に強いなどのメリットもあります。
なおサビや腐食に強いステンレス鋼は他にも存在しますが、SUS304よりも値段は高いです。
コストパフォーマンスの高さからも、SUS304はさまざまな製造現場で採用されています。
SUS304の機械的性質を以下に示します。
| 0.2%耐力(N/mm2) | 205≦ |
| 引張強さ(N/mm2) | 520≦ |
| 伸び(%) | 40≦ |
(参照:日本製鉄グループ 「一般ステンレス鋼(SUS304,SUS316)」より)
そもそも「ステンレス」とは?
ステンレスは、鉄をベースにクロムやニッケルを含有した合金素材です。
錆びにくいという特徴から「Stainless」という名前が付きました。耐食性や耐久性に優れるのに加え、強度が高く磁気を帯ないという性質も持ちます。
錆びにくく汚れが付きにくいことから、メンテナンス性に優れ、用途によっては表面処理などをせずそのまま使うこともできます。
オーステナイト系ステンレス全般にも共通しますが、SUS304は伸ばしやすく、粘りの強さがあります。
そのため、深絞りや曲げ加工などもしやすく、かつ鉄などの他の材料との溶接性にも優れます。
錆びにくく、低温・高温下でも扱いやすいのも特徴です。
SUS304は伸ばしやすいことから、薄板で使われることが最も多いです。
他にも厚板や棒、管(パイプ)、線、鋳物などにも加工できます。
SUS304は容易に鉄と溶接することができます。
ただし粘性が高く、切削する箇所が硬くなる性質があるため、切ったり削ったりする加工とは相性が悪いです。
(参照:ステンレス協会 ウェブサイトより)
SUS304はステンレス鋼の中でも最も流通量が多く、さまざまな用途で使われています。
具体的には、以下のような用途です。
など
具体的な製品例についても見ていきましょう。
身の回りでは、以下のような場所でSUS304が使われています。
など
工業用途では、以下のような場所でSUS304が使われています。
など
ミスミグループ本社が運営する機械加工品の調達支援サービス「meviy(メヴィー)」は、「SUS304(H)」の取り扱いを開始しました。
この「SUS304(H)」は薄さ0.05〜0.1ミリメートルと、曲げられるほど薄い素材です。
これにより、マイクロメートル(マイクロは100万分の1)単位で隙間が調整できる薄板「シムプレート」の調達が可能となります。
SUS304はクロムを18%以上、ニッケルを8%以上含む鋼材です。
SUS304は別名「18-8ステンレス(18Cr-8Ni)」と呼ばれます。
この「18-8」が意味するのが「クロム18%以上、ニッケル8%以上」です。
特にクロムは錆への強さに影響するため、耐食性を評価するのに重要な数値です。
SUS304には以下のような表面処理が行えます。
さまざまな表面処理に対応することも、SUS304が広く使われている理由の1つです。
2021年現在、SUS304の価格は値上がり傾向にあります。
ステンレスメーカー大手の日鉄ステンレスは、2021年3〜5月契約分について、SUS304のステンレス線材を1トンあたり2万5,000円引き上げると発表しました。
(出典: 日本経済新聞 2021年3月3日 20:36「日鉄ステンレス、薄板・厚板を再び値上げ」)
背景にはニッケルなどの主原料が値上がりしていることがあります。
ニッケルやクロムが含まれる金属は、値上がり傾向が続くでしょう。
ステンレス全般の特徴として、錆びない・腐食しない・加工性が良いことなどが挙げられます。
ここではSUS304以外のステンレス「SUS430」「SUS316」の特徴や用途について解説します。
SUS430は18クロム系のステンレスで、熱処理により硬化することがほとんどなく、焼きなましの状態で使用されます。
また、マルテンサイト系ステンレスより成形加工性や耐食性が優れていて、溶接性も比較的良好であるため、一般耐食用として広く用いられています。
具体的には薄板や線の形で、以下のような用途で使われるのが一般的です。
など
SUS316はモリブデンを添加し、錆びにくさなどを向上させたステンレス鋼です。
ステンレスが錆びにくいのは、「不動態被膜」と呼ばれる薄い酸化膜に表面を覆われているためです。
SUS316に含まれているクロムがこの酸化膜を作ることによって、傷が付いても自己修復し、錆を防ぐことができます。
SUS316はモリブデンとニッケルの含有量がSUS304よりも多いため、腐食などに対する耐性はより高いです。
SUS316は錆びにくい特性を活かし、以下のような用途で使われます。
など
(参照:日章アステック株式会社「主要なステンレス材料(SUS304/SUS316L)について」より)
SUS304は通常の冷間プレスにおいて、潰せば潰すほど組織が変化して磁化したり、硬度が上昇したりする性質があります。
シチュエーションによっては加工しづらいのがSUS304のデメリットです。
一方で、温間加工では磁性を帯びず、硬度はHV(ビッカース硬さ)350〜400程度を上限に止まることも分かっています。
つまり、この性質をうまく生かせば、デメリットをメリットに変えられる可能性があります。
そこで、SUS304を300℃前後と比較的低温の条件で温間加工することにより、プレス加工品を精密に成形する技術も開発されています。
この方法であれば、SUS304の磁化や加工硬化を抑えることが可能です。
SUS304は今後、医療機器や精密機器、自動車などの部品として利用が見込まれています。
ステンレス鋼は品種ごとにそれぞれ優れた機能や加工特性などがありますが、加工技術の進化によってデメリットを克服したり、新たな合金が生み出されたりしています。
ここでは、より発展的なステンレス鋼の使い方を導入した事例を紹介します。
日本製鉄は強度と耐食性が高い省合金型2相ステンレス鋼「YUS2120」を用い、継ぎ目のない鋼管を開発しています。
YUS2120は省合金型ですが、強度がSUS304の2倍もあり、耐食性もSUS304と同等以上です。
既に中堅造船会社みらい造船(宮城県気仙沼市)の船舶陸揚げ・進水設備用オートテンションウインチの油圧配管に採用されています。
YUS2120はSUS304よりも強度が高い分、管の厚さを最大で半分程度まで減らせます。
原料として添加する合金の量が一般的なステンレス鋼より少なくて済むため、省資源化にも貢献できるでしょう。
エア・ウォーターの子会社であるエア・ウォーターNVは、ハイブリッド車用ターボチャージャー(過給器)部品向けに、独自の表面処理加工技術を開発しました。
独自技術「CR-NITE(ナイト)」により、ステンレス部品に約1000℃の耐熱性を持たせて、ニッケル基合金などの高価な材料との置き換えを狙います。
各自動車メーカーはハイブリット車のエネルギー効率を高める過給器の開発を進めています。
エア・ウォーターNVが実施した耐高温酸化評価試験によると、CRナイト加工を施したステンレス(SUS304)製の部品は、未加工品に比べ酸化の進行を40分の1以下に抑えることが確認されています。
(参照:エア・ウォーターNVのウェブサイト)
SUS304は錆や腐食に強く、加工性に優れることから、さまざまな用途で用いられています。
加工時の磁化や硬化などのデメリットもありますが、加工技術の進化により解決が期待できます。
SUS304の特性を理解しておくことで、製造現場での課題解決に活かせるかもしれません。
このウェブサイトのコンテンツは、当社の価値観や活動を反映しております。
無断での転載や使用は一切禁止します。
転載を希望する場合は、事前の連絡と許諾の取得をお願いします。